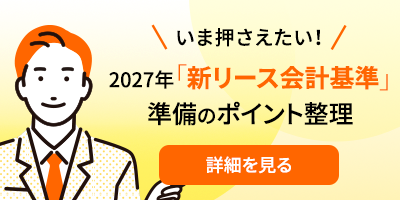第20回 間接費の配賦
-

【5分で納得コラム】今回のテーマは、「間接費の配賦」です。
内容
間接費配賦は、特定の製品や部門に直接紐づけられない費用を合理的に割り振り、実態に即した損益構造を明らかにする重要な管理会計プロセスです。FP&A部門は、配賦ルールの設計・分析・改善を通じて、部門別採算性の見える化や新規事業の採算評価、予算統制の強化を実現します。適切な配賦は、原価把握の精度向上や責任単位の公平な評価を可能にし、撤退・投資判断、コスト最適化などの戦略的意思決定を支える基盤となります。本稿では間接費の配賦について解説します。
第20回 間接費の配賦
1. 間接費配賦の基本概念
(1)間接費とは
間接費とは、特定の製品やサービスに直接紐づけることが難しい費用です。例えば、工場の光熱費、人事部門の人件費、本社の賃料などがこれに該当します。これらは、すべての事業や製品にまたがって発生しているため、何らかのルールで「配賦(分配)」する必要があります。
(2)配賦の目的
管理会計において間接費の配賦は、企業活動の実態を正確に把握し、より良い経営判断を下すために不可欠なプロセスです。特にFP&Aにおいては、この配賦の仕組みを適切に設計・分析し、全社的な資源配分や業績評価に活用することが求められます。間接費配賦の目的は以下に整理されます。
①原価把握の精度向上
企業が製造・提供する製品やサービスには、それぞれ異なる間接コストが関わっています。例えば、製品Aは多くのカスタマーサポートや物流コストを必要とする一方、製品Bはシンプルな構造で追加的な管理費が少ないということもありえます。こうした実態を把握するには、直接費だけでなく間接費を適切に配賦し、製品ごとの「真の原価構造」を明らかにする必要があります。FP&Aはこの配賦設計を通じて、製品ポートフォリオの見直しや価格戦略の妥当性を裏付ける役割を担います。
②損益責任単位の評価
多くの企業では部門別や事業ライン別の採算管理が求められますが、間接費を含めた損益管理がなければ、実態を正しく評価できません。たとえば、営業部門が利益を出しているように見えても、実際には本社の広告宣伝費やIT費用などが配賦されると、赤字であるということもありえます。FP&Aは、こうした「責任単位」の実質的な業績を見える化し、組織全体のパフォーマンスを整合的に評価する仕組みを設計します。また、配賦基準の透明性と納得性を高めることも、各部門が自律的に目標管理を行うためには重要です。
③戦略的意思決定の支援
例えば、ある製品ラインが赤字であるか否か、あるいは新規事業に投資すべきかといった判断は、単なる収益や売上だけでなく、配賦された間接費を含めた「正味の収益性」に基づく必要があります。FP&Aは、配賦後の損益情報を活用して、撤退・継続の判断材料を提供したり、利益貢献度の高い事業に資源を集中させる戦略を提案したりします。また、価格改定、外部委託の可否、コスト削減策の選定など、多様な意思決定においても、配賦された間接費の影響を定量的に評価する視点が不可欠です。
2. 配賦方法の種類
FP&A部門が分析対象とするためには、適切な配賦方法を採用する必要があります。代表的な方法は以下の通りです。
表 間接費の配賦方法
配賦方法 特徴 直接配賦法 すべての間接費を1つの基準(例:売上比率、人員数)で按分する 階梯式配賦法 間接部門の提供関係に序列を設けて段階的に配賦 相互配賦法 各部門の相互サービスを完全に考慮して配賦 活動基準原価計算(ABC) 各活動に基づいて間接費をトレースし、最終的に製品・顧客単位に配賦する 3. FP&Aと間接費配賦の関係
FP&Aは、間接費配賦の設計・分析・改善提案を通じて、全社のパフォーマンスマネジメントに貢献します。
(1) 配賦設計フェーズ
この段階では、企業内で発生する多様な間接費を、どの基準でどの部門・製品・事業へ割り振るかという「配賦ロジック」を構築します。これは部門別損益計算書(部門別PL)や事業別収益性の把握に向けた基盤であり、極めて重要なステップです。例えば、人事部門や情報システム部門、経営企画部門などの管理間接費を、従業員数、システム利用数、売上規模といった定量的な指標に基づき各部門へ配賦するケースが一般的です。
また、この配賦ロジックは単なる計算式ではなく、経営方針を反映する戦略的ツールでもあります。例えば、成長が見込まれる戦略事業に対して間接費配賦を一部免除し、投資的コストを集中的に投入するといった意思決定も含まれます。FP&Aには、こうした経営的意図を踏まえつつ、合理的で説明可能な配賦基準を設計することが求められます。
(2) 分析フェーズ
このフェーズでは、各事業・部門の実質的な収益性(=直接費+間接費)を評価し、原価のトレンドや他社比較(ベンチマーク)を行います。これにより、部門間や事業間の効率性や収益構造の違いを明らかにします。
(3) 改善提案フェーズ
分析結果に基づき、配賦ロジックの簡素化・透明化を図り、経営層や現場の理解促進を支援します。また、活動基準原価計算(ABC)の導入や、Shared Services、BPOといった間接費最適化の施策を提案し、全社的なコスト構造の改善を実現します。
4. 実務での応用例(FP&Aの観点)
(1) 部門別損益の見える化
FP&A部門は、人件費、オフィス費用、IT関連費などの間接費を本社から各事業部門へ適切に配賦し、部門ごとの実質的な損益構造を可視化します。これにより、一見黒字に見える部門が、本社コストの配賦を反映すると赤字となるケースも明らかになります。こうした分析を通じ、赤字の主要因となるコスト項目(例:ITライセンス費用、オフィス賃料など)を特定し、改善策を提案します。
具体的には、複数部門で重複しているIT契約の統合によるスケールメリットの創出や、オフィスの集約・移転など、費用最適化につながる施策が導き出されます。
(2) 新規事業の採算評価
新規事業の立ち上げ時には、売上や変動費だけでなく、将来的に配賦される間接費も加味して黒字化の見通しを立てる必要があります。FP&Aは、人事、経理、ITサポート費などの本社コストが将来的にどの程度割り振られるかを想定し、それらを含めた損益分岐点をシミュレーションします。
これにより、黒字転換に必要な売上規模や利益率といった具体的な目標値を提示するとともに、あらかじめ撤退基準を設定できます。こうした分析結果は、経営層が新規事業の継続可否を定量的根拠に基づいて判断するための重要な材料となります。
(3) 予算管理とコストセンター管理
予算管理においては、部門ごとの費用責任を明確化することが不可欠です。FP&Aは、配賦後の間接費を部門別に詳細分解し、コストセンター単位での予算管理に反映します。この際、単なる費用管理にとどまらず、配賦後のROIC(投下資本利益率)や貢献利益率などのKPIを導入することで、より戦略的な管理が可能になります。
これにより、部門責任者は自部門の資源配分やコスト構造に対して説明責任を果たしつつ、合理的な意思決定を行えるようになります。結果として、FP&Aは配賦の仕組みを通じて、企業の予算統制力を高め、経営層と現場の双方に納得感のある管理基盤の構築に貢献します。
FP&A部門における間接費配賦の役割は、単なる「費用の分け方」ではなく、経営意思決定を支える戦略的な分析・設計・改善活動です。部門別採算性の可視化、事業評価、全社最適化に向けた基盤として、精緻かつ納得感のある配賦ルールを構築・運用することが、FP&Aの付加価値を高めるポイントとなります。
執筆陣紹介
- 仰星コンサルティング株式会社
-
仰星コンサルティング株式会社は、仰星監査法人グループのコンサルティング会社であり、
クライアントの成長、再生を成功に導くために、付加価値の高いソリューションサービスを提供いたします。
主な業務として、海外子会社等の調査や内部監査支援などのリスクアドバイザリーサービス、
M&A後の業務統合を支援するPMIや決算早期化、IT導入を支援するマネジメントコンサルティングサービス、
買収・組織再編を支援するファイナンシャルアドバイザリーサービス、
上場を成功に導くIPO支援サービスを展開しております。 -
≪仰星コンサルティング株式会社の最近のコラム≫
※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。