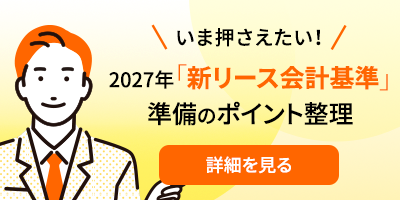「租税調査会研究報告第42号「欠損金に関する論点整理」」の概要
-

【5分で納得コラム】今回のテーマは「租税調査会研究報告第42号「欠損金に関する論点整理」」の概要です。
内容
「租税調査会研究報告第42号「欠損金に関する論点整理」」の概要
1. はじめに
日本公認会計士協会は、2025年7月30日に「租税調査会研究報告第42号「欠損金に関する論点整理」」を公表しました。当該研究報告では、①我が国における欠損金額の制度の概要、②自社で生じた欠損金に関する法規定、使用制限、③他社で生じた欠損金を自社に引き継ぐ際の法規定及び使用制限、④グループ通算制度における欠損金に関する法規定及び使用制限、⑤我が国の欠損金の繰越控除制度と海外における同制度との比較を視点とした研究報告です。
今回は、当該研究報告のうち、①~③についてご紹介します。2. 我が国における欠損金額の制度の概要
【欠損金の取扱い】
当該事業年度の益金の額ー当該事業年度の損金の額
⇒ プラス分を「所得」(法人税法第22条第1項)
マイナス分を「欠損金額」(法人税法第2条第19号)上記の欠損金額は、法人税法上「繰越控除」の適用が認められています。「繰越控除」とは、翌期以降の事業年度に欠損金を繰り越して、所得が生じた事業年度において損金として控除する制度です(法人税法第57条第1項)。
一方で、当期に生じた欠損金額を過年度の所得が生じた事業年度に繰り戻して法人税の還付を求める制度である「繰戻し還付」の適用も法人税法上認められています(法人税法第80条)。
欠損金の繰戻し還付と繰越控除のいずれかを適用するかは、法人の任意選択ですが、欠損金の繰戻し還付には以下のメリットとデメリットが存在します。
メリット 欠損金の繰戻し還付による収入は益金不算入(法人税法第26条第1項第4号)となるため、法人の資金繰り改善に役立つ。 デメリット ①税務調査の対象となりやすい(法人税法第80条第10項)
②地方税において繰戻し還付が認められてない
⇒・地方税の欠損金等の控除明細書との齟齬
・控除対象還付法人税額等が記載された明細書を作成し、法人住民税に関する繰越控除額を把握する必要が生じる
⇒上記のことから処理が煩雑になる3. 自社で生じた欠損金に関する概要
内国法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した青色申告書を提出した事業年度において生じた欠損金額があり、その後も連続して確定申告書を提出し、欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を保存している場合には、その欠損金額に相当する金額は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます(法人税法第57条第1項)。
損金算入限度額 中小法人等 所得金額の100%相当額
(法人税法第57条第11項)中小法人等以外 各事業年度の所得の金額の50%に相当する金額
(法人税法第57条第1項ただし書き)また、その事業年度において繰り越された欠損金額が二以上の事業年度において生じたものからなる場合には、そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金算入を行うものとされています(法人税法基本通達12-1-1)。
4. 他社で生じた欠損金を自社に引き継ぐ際の概要
法人税法においては、組織再編行為の前後における経済的実態に実質的な変更がないものと認められる一定の適格要件を満たしている場合には、課税関係が継続するものとされ、一定の適格要件を満たしていない場合には非適格として法人税の課税対象になるものとされています。
税制上の適格要件を満たしている組織再編の手法別の繰越欠損金の取扱いは、下記のとおりです。
組織再編の手法 引継ぎ 使用 適格合併
(法人税法第2条第12号の8)被合併法人の繰越欠損金を合併法人へ引継可
(引継制限あり)合併法人の繰越欠損金は合併法人で使用可
(使用制限あり)適格分割
(法人税法第2条第12号の11)分割法人の繰越欠損金は分割承継法人に引継不可 分割承継法人の保有する繰越欠損金は使用可
(使用制限あり)適格現物出資
(法人税法第2条第12号の14)現物出資法人の繰越欠損金は被現物出資法人に引継不可 被現物出資法人の保有する繰越欠損金は使用可
(使用制限あり)適格現物分配
(法人税法第2条第12号の15)現物分配法人の繰越欠損金は被現物分配法人に引継不可 被現物分配法人の保有する繰越欠損金は使用可
(使用制限あり)適格株式交換等
(法人税法第2条第12号の17)資産等の移転が生じないため論点なし 資産等の移転が生じないため論点なし 5. 我が国における欠損金制度の課題と望まれる改正点
<欠損金の繰越控除における期間制限>
法人税の課税期間を事業年度としているのは、課税の便宜上の要請で人為的に区切りを設けたものと考えられますが、企業利益に対する課税は、企業の存続期間を通じて中立的であることが望まれています。
このような観点からは、欠損金の繰越控除期間をできる限り長期間とすることが望まれます。本研究報告では、米国、英国、ドイツ及びフランスは無制限としていることを鑑み、これらの諸外国の立法例を参考とし、帳簿等の保存期間を含めた執行上の問題を考慮して再検討されるべきであると述べられています。<欠損金の繰越控除における損金参入制限>
資本金が1億円調の法人については繰越欠損金の控除限度額が課税所得の50%に制限されていますが、この資本金の判定基準日が事業年度末であるため、決算間際での減資により控除限度額制限を回避する動きが見られ、課税の公平性の観点から問題提起されています。多額の先行投資を要する成長企業において、本業が上向きかけた際に欠損金の繰越控除制限による税金負担が生じたとしたら、税制が企業成長の足かせともなりかねません。
したがって、本研究報告では、成長企業に対しては、一定の要件を設けたうえで繰越欠損金の控除限度額制限を撤廃することも検討されるべきであると述べられています。<合併等の組織再編成における欠損金の使用・引継制限>
支配関係形成後5年超経過後は、特定資産譲渡等損失額に相当する金額から成る欠損金額や被合併法人から引き継いだ欠損金額については、使用・引継制限を設けておりませんが、租税回避行為と認められる組織再編成に引き継いだ欠損金額については包括的否認規定(法人税法第132条及び第132条の2)が発動され、訴訟に至るケースが散見されます。
課税の公平性を保つため、「組織再編成に係る行為又は計算の否認」(法人税法第132条の2)といった包括的否認規定を発動する必要があるのであれば、課税庁はその否認規定に関する解釈指針を定め、納税者に対して周知することを検討すべきであると述べられています。<災害により生じた損失に係る欠損金額の繰戻し還付制限>
災害により生じた欠損金の繰越控除であれば、青色申告書を提出することで将来課税所得との減殺効果を得ることができますが、繰戻し還付については、青色申告法人で、かつ中小法人でなければ適用することができない規定となっています。
近年、自然災害が多発する状況を鑑み、災害損失に災害後において事業を回復するための費用を含めるなど制度としての利用可能性を高める措置が検討されるべきであると述べられています。
(参考情報)
日本公認会計士協会HP
租税調査会研究報告第42号「欠損金に関する論定整理」の公表について
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20250730ibc.html
執筆陣紹介
- 仰星監査法人
-
仰星監査法人は、公認会計士を中心とした約170名の人員が所属する中堅監査法人です。全国に4事務所(東京、大阪、名古屋、北陸)2オフィス(札幌、福岡)を展開しており、監査・保証業務、株式上場(IPO)支援業務、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、パブリック関連業務、コンサルティングサービス、国際・IFRS関連業務、経営革新等認定支援機関関連業務などのサービスを提供。
-
≪仰星監査法人の最近のコラム≫
※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。